しっかり寝たのに、朝からだるい
週の半ばにはもうクタクタ
休日もだるくてやる気が出ない
そんな“慢性的な疲れ”を感じていませんか?
年齢や忙しさのせいと思いがちですが、実は“栄養バランスの乱れ”が隠れていることも。
体のエネルギーをつくる栄養が足りなかったり、ストレスや血流の悪化で酸素や栄養が細胞まで届きにくくなっていたり——。
こうした小さな“エネルギー不足”が積み重なることで、だるさや集中力の低下を招きやすくなるのです。
でも大丈夫。
毎日の食事を少し工夫するだけで、疲れにくい体を取り戻すことは十分に可能です。
たとえば、エネルギー代謝を助けるビタミンB群や鉄、たんぱく質を意識してとることで、体の「元気スイッチ」をしっかり押すことができます。
この記事では、
- 疲れがたまりやすくなる原因
- 疲労回復に役立つ栄養素と食材
- 1日の食事でできる実践法
を薬剤師の視点でわかりやすく解説します。
仕事や家事に追われる毎日でも、食事の力で少しずつ“軽やかな自分”を取り戻しましょう。
疲れにも種類がある?ー疲れの種類と主な原因

「疲れた…」とつぶやいた時、その疲れは「疲労」と「疲労感」どちらでしょうか?
「何言っているの?どっちも同じでしょ?」と思うかもしれませんが、この2つ、実は違うものなんです。
「疲労」と「疲労感」それぞれに原因や対策も異なります。世の中にはいろいろな疲れ対策の情報がありますが、どちらの疲れかが分からないまま実践しても、なかなか改善につながりません。それぞれの違いについて詳しく紹介しますので、まずはあなたの「疲れた…」がどちらの疲れなのかを知るところから始めましょう。
疲労≒身体的な疲れ
学生時代の体育の時間、たくさん動いて「疲れた…」となった経験があると思います。また、テスト前に何時間も勉強を続けて疲れたこともあるかもしれません。これらの疲れは実際に肉体や頭脳が疲れた状態で、「疲労」と呼ばれます。
これは簡単に言ってしまえば、身体がエネルギー不足な状態。この状態では、筋肉の収縮力が低下したり、集中力が低下したりと活動のパフォーマンスが落ちてしまいます。
対策としては、バランスの良い食事でエネルギー補給をすることと、十分な休養・睡眠を取ること。また、血流を促すためにストレッチやウォーキングなど軽めの運動も効果的です。
【定義】
生体の活動能力が一時的に低下している客観的な状態。
例:筋肉の収縮力低下、集中力や判断力の低下など。
【原因】
筋肉や神経の酷使
過度な集中作業
感染症や代謝異常
栄養・休養不足
【対策】
十分な休養・睡眠
バランスの良い食事(エネルギー補給)
適度な運動(回復力を高める)
 まっきー
まっきー過度な活動や栄養・休養不足で実際に肉体や頭脳が疲れ、筋肉の収縮力低下、集中力や判断力の低下といった症状が出ている状態のことを、「疲労」と呼びます
疲労感≒精神的な疲れ
仕事の納期に追われたり、人間関係に悩まされたり。現代人はストレスを抱えがちです。ストレスを抱えすぎると、夜しっかり寝たはずなのに、「朝から疲れてる」「やる気がでない」と精神的な疲れを感じることはありませんか?
この、「肉体的には元気なはずなのに、なんだか疲れていると感じる」状態のことを「疲労感」と呼びます。
過度なストレスを抱え続けていると、自律神経のバランスが乱れます。交感神経が優位な状態が長く続くと、常に体が緊張し、リラックスできなくなるのです。結果として、体の疲れよりも「なんとなくやる気が出ない」「頭が重い」といった形で表れます。
対策としては、適度にストレスを発散すること。それから規則正しい生活リズムを作ることで、自律神経の乱れを整えるのも良いでしょう。栄養面では、ビタミンCなどストレス耐性に関与する栄養素を摂るのがおすすめです。
【定義】
疲労を主観的に自覚する感覚、心理的な訴え
例:だるい、重い、やる気が出ないなど
【原因】
疲労に加え、情動や心理状態の影響を強く受ける
抑うつ、不安、慢性ストレス、睡眠の質低下などが関与
【対策】
生活リズムの調整
ストレスマネジメント(趣味、カウンセリング、ビタミンCなどストレス耐性に関与する栄養摂取)
症状が長引く場合は医療機関を受診(貧血・甲状腺疾患・慢性疲労症候群などを鑑別)



肉体的な疲労の有無に関わらず、”疲れている”と感じている状態を、疲労感と呼びます
「疲労」=肉体や頭脳が実際に疲れている状態
「疲労感」=”疲れている”と感じている気持ち・感覚
疲労と疲労感の違い、ご理解いただけたでしょうか?自分の疲れがどちらなのか把握できたら、より適した対策を選んで実践してみてください。
次の章からは、食事でできる疲れ対策をご紹介します。
疲労回復に関わる主な栄養素


「疲労」と「疲労感」どちらの疲れにも影響し得るのが、栄養バランスの乱れです。
食事の偏りや、忙しさから食事を抜くことが続くと、エネルギーを作るために必要なビタミンB群や鉄、たんぱく質などが不足しがちに。代謝に必要な栄養素が足りず、エネルギーがうまく生み出せなくなると、肉体的な疲労状態に陥ります。
そのため、疲労回復にはエネルギー源となる糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素は必須。さらにこれらを体内でエネルギーに変化させ、効率良く利用できるような栄養素をとることが大切です。
また、ビタミンCやビタミンB群、マグネシウムなどストレス耐性に関与する栄養素も重要です。これらが不足するとストレスに弱くなり、「からだが重い」「やる気が出ない」といった疲労感を感じやすくなる恐れがあります。
このように様々な栄養素が疲労回復に関わっていますが、代表的なものを表にまとめました。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB1 | 糖質をエネルギーに変える | 豚肉、玄米、にんにく |
| ビタミンB2 | 脂質代謝・細胞の修復 | 卵、納豆、乳製品 |
| ビタミンB6 | たんぱく質代謝・神経の働きを整える | 鮭、バナナ |
| 鉄 | 酸素を全身に運び、エネルギー維持 | 赤身肉、レバー、小松菜 |
| マグネシウム | 代謝をサポート・筋肉の緊張を緩める・ストレス耐性に関与 | 豆腐、ナッツ |
| クエン酸 | 代謝サイクルを助ける・乳酸の分解 | レモン、梅干し |
| ビタミンC | 抗酸化作用で細胞のダメージを防ぐ | 柿、キウイ、ピーマン |
| トリプトファン | 幸せホルモン「セロトニン」の材料 | 大豆、乳製品、バナナ、鶏むね肉 |
ビタミンB群:エネルギーづくりの要
ビタミンB群は、糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える過程で欠かせない存在です。なかでも ビタミンB1 は「疲労回復ビタミン」とも呼ばれ、糖質の代謝をサポートします。豚肉、玄米、大豆製品、にんにくなどに多く含まれます。
また ビタミンB2 は脂質の代謝を、B6 はアミノ酸の代謝を助け、筋肉の疲労回復や神経の働きをサポートします。卵やまぐろ、バナナなどを組み合わせてとると良いでしょう。



三大エネルギー源(糖質・脂質・たんぱく質)とビタミンB群はセットで働くので、一緒に摂ると効果的です
鉄・亜鉛・マグネシウム:エネルギーを運び、使うために
エネルギーを「つくる」だけでなく、それを「届ける」「使う」ために重要なのがミネラル類です。
鉄 は酸素を運び、体中の細胞がしっかり働くために必要不可欠。鉄が不足すると酸欠状態のようになり、全身がだるく感じやすくなります。赤身肉やレバー、ひじき、小松菜などがおすすめです。
亜鉛 は体内の酵素を活性化させ、疲労回復や免疫機能の維持に関わります。牡蠣や牛肉、ナッツ類などから補いましょう。
マグネシウム は筋肉や神経の働きを助け、ストレスによる緊張を和らげる作用があります。豆類、海藻、アーモンドなどに多く含まれます。



亜鉛やマグネシウムはストレス耐性にも関与します
ビタミンC・E:ストレスと戦う栄養素
疲労感には精神的ストレスが大きく関わります。そんなときに頼れるのが ビタミンC や ビタミンE。これらは抗酸化作用を持ち、体内で発生する活性酸素を取り除いて細胞のダメージを防ぎます。ストレス耐性にも関与しているため、肉体的・精神的どちらの疲労回復にも効果的です。
ビタミンCはキウイや柿などの果物やピーマン、ブロッコリーなどに。ビタミンEはナッツ類や植物油に多く含まれます。



ビタミンCとビタミンEは合わせて摂ると、相乗効果で抗酸化作用が高まります
疲れを感じた日におすすめの食材・メニュー


疲れを感じたときは、単に「たくさん食べる」よりも、栄養バランスのよい食材を上手に組み合わせることがポイントです。ここでは、日常の食卓で取り入れやすい“疲労回復の味方”と具体的なおすすめメニューをご紹介します。
■ 豚肉:エネルギー代謝を助ける代表格
疲労回復ビタミンと呼ばれるビタミンB1が豊富。ごはんなどの糖質と一緒にとることで、エネルギーを効率よく作れます。にんにくや玉ねぎの成分「アリシン」と組み合わせると、ビタミンB1の吸収がアップ。
おすすめメニュー
- 豚のしょうが焼き
- 豚ニラ炒め
- 豚汁
■ 魚介類:鉄・亜鉛・たんぱく質をまとめて補給
まぐろやかつお、鮭などの魚には良質なたんぱく質が豊富で、筋肉や臓器の修復をサポートします。
また、かきやあさり、しじみには鉄や亜鉛が多く含まれ、貧血による倦怠感の改善にも役立ちます。
おすすめメニュー
- まぐろの山かけ
- しじみの味噌汁
- 鮭のちゃんちゃん焼き
■ 大豆製品:回復のベースを整える
豆腐、納豆、味噌などの大豆製品は、植物性たんぱく質とビタミンB群、マグネシウムをバランスよく含みます。脂質が控えめで消化も良いので、疲れて食欲がないときにも取り入れやすい食材です。
おすすめメニュー
- 冷奴
- 納豆ごはん
- 味噌煮込みうどん
■ 緑黄色野菜・果物:抗酸化とストレスケアに
ブロッコリー、ピーマン、トマト、柑橘類、キウイなどには、ビタミンCやβ-カロテンなどの抗酸化成分が豊富。これらは、ストレスや紫外線などで発生する活性酸素から体を守り、疲れの蓄積を防ぎます。
おすすめメニュー
- 豚しゃぶサラダ
- 野菜スープ
- キウイ×ヨーグルト
■ 玄米・雑穀・芋類:持続するエネルギー源
糖質はエネルギーのもとですが、白米や砂糖のように吸収が早すぎると血糖の乱高下が起こり、かえって疲労感を招くことも。玄米や雑穀、さつまいもなどはゆっくり吸収され、ビタミンB群や食物繊維も豊富です。主食を少し工夫するだけでも、疲れにくい体づくりに役立ちます。
おすすめメニュー
- 雑穀米カレー
- 鶏肉とさつまいものシチュー
- ポテトサラダ
疲れている時には手間のかかる食事を準備するのも大変ですよね。そんな時には「手軽に作れて、体の中から元気が出る」ことを重視して選びましょう。
1日の中での取り入れ方


疲れをためないためには、「何を食べるか」だけでなく、いつ・どんな形で取り入れるかも大切です。1日のリズムに合わせて、無理なく栄養を整えましょう。
朝は代謝を動かす大事なタイミング。
糖質・たんぱく質・ビタミンB群を組み合わせるのがコツです。
・納豆ごはん+味噌汁+目玉焼き
→エネルギー産生をスムーズに。
・バナナ+ヨーグルト+豆乳
→忙しい朝にも手軽にビタミンB群&マグネシウム補給。
昼は活動量が最も多い時間帯。
主食を玄米や雑穀にして、たんぱく質をしっかり。
・豚の生姜焼き+雑穀ごはん+ブロッコリーの胡麻和え
→B1とアリシンで代謝促進。
・鮭のおにぎり+具だくさん味噌汁
→コンビニでも買えて、たんぱく質・ミネラル・野菜が摂れる組み合わせ。
夜は1日の疲れを修復する時間。
消化の良い食事とミネラル補給を意識しましょう。
・豆腐としめじの味噌鍋+雑穀ごはん
→たんぱく質・ビタミンB群・マグネシウムが一度に。
・さばの味噌煮+小松菜のおひたし+けんちん汁
→鉄やビタミンB群で回復力アップ。



その他、間食にはナッツやドライフルーツがおすすめ。マグネシウムやビタミンEが補え、エネルギー切れを防ぎやすくなります
まとめ|“疲れにくい体”は毎日の食事から
疲れを感じるのは、体が「少し休ませて」とサインを出している証拠。
無理に頑張る前に、まずはエネルギーを生み出すための栄養を見直してみましょう。
- エネルギー代謝を助けるビタミンB群
- 酸素や栄養を運ぶ鉄・亜鉛・マグネシウム
- ストレスや酸化を防ぐビタミンC・E
- 回復の土台をつくるたんぱく質
これらを日々の食事の中でバランスよくとることで、
「なんとなくだるい」「疲れが抜けない」という状態から少しずつ抜け出せます。
ポイントは、特別な食事をすることよりも、毎日の“ちょっとした積み重ね”。
朝の味噌汁に豆腐を加える、昼に雑穀ごはんを選ぶ、夜に野菜をもう一品添える——
そんな小さな工夫が、確実にあなたの回復力を高めてくれます。
体は、食べたものでつくられます。
「食べること」でエネルギーを補い、「眠ることで」回復する。
その基本を整えるだけで、体も心も驚くほど軽くなります。
明日の自分のために、今日の食卓を少し整えてみましょう。
疲れと上手につきあう第一歩は、あなたの“いつものごはん”から始まります。
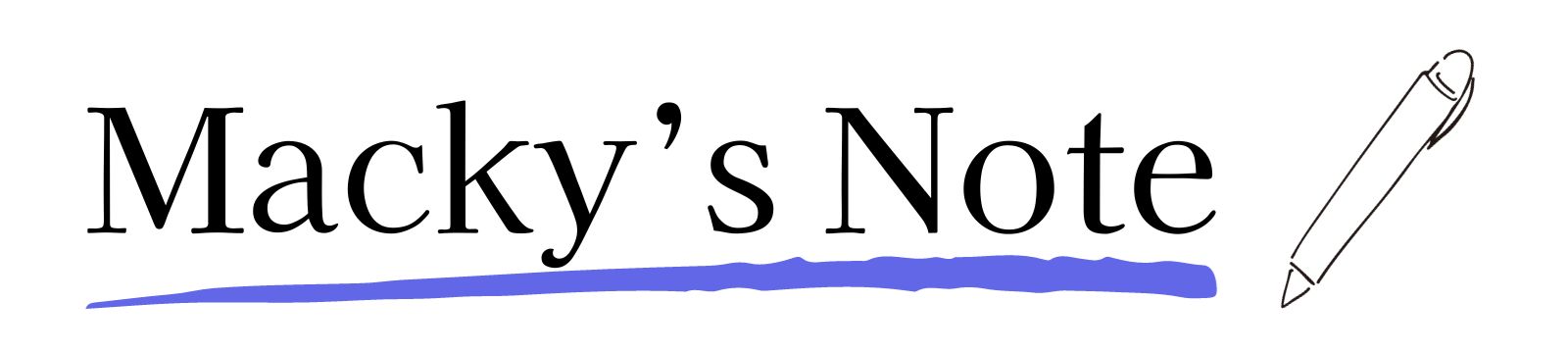
.jpg)

-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)

改-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)