私たちの体をつくる「たんぱく質」。
そのはたらきや必要量、摂りすぎ・不足のリスクを3回に分けてわかりやすく解説しています。
▶️ 第1回|たんぱく質の働きとは? 基礎からわかる3つの役割
▶️ 第2回|1日のたんぱく質摂取量の目安は? 食材別たんぱく質量とバランスのとり方
▶️ 第3回|たんぱく質が不足・摂りすぎるとどうなる? バランスを崩すリスクと対策
今回は「たんぱく質の摂取量」について詳しく見ていきます。
たんぱく質ってどれくらい摂ればいいの?
肉や魚にはどれくらい含まれているんだろう?
毎日の献立の参考が知りたい
こんな疑問に対して、薬剤師がわかりやすく解説していきます。
▼この記事でわかること▼
・たんぱく質の摂取目安は1食あたり25〜35g程度
・鶏むね肉や魚、豆製品を組み合わせて自然に摂取
・不足・過剰を防ぐには「主菜1品+豆製品」を意識
より詳しく知りたい方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
それでは、どうぞ!
1日のたんぱく質摂取量の目安(男女別)

たんぱく質は私たちの体を作るのに大切な成分であることはご存知の方も多いと思います。
ですが、毎日の食事でどのくらい摂るべきなのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか?
実はたんぱく質などの栄養素の摂取量について、厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」で目安となる基準値を設定しています。そこでは、○○量というのがいくつかありますが、注目して欲しいのは推奨量と目標量。詳しい定義はややこしいので、簡単に違いを説明すると下のようになります。
推奨量:健康維持を目的とした摂取量
目標量:生活習慣病予防を目的とした摂取量
推奨量と目標量では設定されているたんぱく質の摂取量が異なるため、それぞれ見ていきましょう。
たんぱく質の推奨量(健康維持を目的)
推奨量は健康な人々のほとんどが不足しないと推定される量のこと。つまり、たんぱく質の摂取量がこの推奨量を下回る生活を続けていると、たんぱく質不足となって健康維持ができなくなる恐れがあります。
成人における1日あたりのたんぱく質の推奨量を下の表にまとめました。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~64歳 | 65g | 50g |
| 65歳以上 | 60g | 50g |
1歳から17歳までの推奨量が知りたい方は下の表をご覧ください。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1~2歳 | 20g | 20g |
| 3~5歳 | 25g | 25g |
| 6~7歳 | 30g | 30g |
| 8~9歳 | 40g | 40g |
| 10~11歳 | 45g | 50g |
| 12~14歳 | 60g | 55g |
| 15~17歳 | 65g | 55g |
たんぱく質の目標量(生活習慣病予防を目的)
目標量は生活習慣病予防のために、当面目指すべき摂取量の範囲とされ、推奨量より大きい数値が設定されていることが多いです。
たんぱく質の目標量は、多くの年代で男女ともに摂取エネルギー量の13〜20%。
たんぱく質は1gあたり4kcalなので、たとえば1日の摂取エネルギーが2000kcalなら、たんぱく質として65〜100gが目標となります。
1日3食で考えると、多くの人は1食あたり25〜35g程度のたんぱく質を摂れると◎
より自分に適した量が知りたい方は、下の表をご覧ください。男女・年代別の摂取エネルギー量をもとに、たんぱく質の目標量をグラムに計算し直して、表にまとめました。
.jpg)
 まっきー
まっきー摂取エネルギー量は、身体活動レベル「ふつう」の人を想定しています
食材別に見る!たんぱく質量の比較


たんぱく質が豊富な食材といえば肉や魚、大豆などが思い浮かびますが、実際にどの程度たんぱく質を含んでいるのでしょうか?
身近な食材にどれくらいたんぱく質が含まれているのかを見てみましょう。
| 食材 | 1食分の目安量 | たんぱく質量(g) | 補足メモ |
|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 約100g | 24.0g | 高たんぱく・低脂質で人気 |
| 豚バラ肉(薄切り) | 約100g | 14.2g | コクがあり脂質多め。エネルギー源にも |
| 銀鮭(切り身) | 約80g | 15.7g | 良質なたんぱく質+ビタミンDも豊富 |
| 鯖缶(水煮) | 1缶(150g) | 31.0g | 良質な脂質(EPA・DHA)も豊富 |
| 鶏卵 | 1個(60g) | 7.4g | 手軽に摂れる完全栄養食 |
| 木綿豆腐 | 1/2丁(200g) | 14.0g | 消化吸収が良く、植物性たんぱく源 |
| 納豆 | 1パック(50g) | 8.3g | 発酵食品として腸活にも◎ |
| 牛乳 | 1杯(200mL) | 6.6g | カルシウムも同時に摂取可 |
| 枝豆(ゆで) | 約100g(さや付き) | 11.0g | 手軽な植物性たんぱく源 |
| ブロッコリー(ゆで) | 約100g | 4.3g | 野菜ではトップクラスのたんぱく源 |
| ほうれん草(ゆで) | 約70g | 2.0g | 鉄・葉酸も豊富で女性に◎ |
| ごはん(白米) | 1膳(150g) | 3.8g | 炭水化物主体だが意外に含む |
肉や魚はやはり1食分あたりのたんぱく質量が多く、効率良くたんぱく質を摂取するのに向いています。ただし、たんぱく質の効率だけを考え同じ食材ばかり食べると、脂質やビタミン、ミネラルに偏りが出てしまいます。また、動物性たんぱく質は消化機能に負担を与えるため、肉や魚ばかりになると腸内環境を悪化させてしまうかもしれません。
肉や魚に比べると少量ですが、野菜類にもたんぱく質が含まれており、食物繊維やビタミンなども摂れるため栄養バランスを整えるのに役立ちます。
健康的にたんぱく質を摂取するためには、動物性+植物性を組み合わせて、色々な食材を食べることがおすすめです。
不足・摂りすぎに注意!たんぱく質のバランスを取るコツ


一般的な食生活を送っていれば、たんぱく質が極端に不足することは多くありません。
ただし、次のような人は不足や過剰に注意が必要です。
- 食事量が少ない高齢者
- 偏食・好き嫌いが多い人
- 食事制限ダイエットをしている人
- プロテインを1日2回以上飲む人
- 腎機能が低下している人
また、動物性たんぱく質に偏ると腸内環境の悪化や腎臓への負担が増えることもあるため、肉・魚・大豆製品をバランス良く組み合わせましょう。
不足や摂りすぎのリスクを詳しく知りたい方は▼こちら▼も併せてご覧ください。


日々の食事で「ちょうど良く」摂るために
たんぱく質は“量よりバランス”が大切です。
毎食に主菜1品+豆製品を取り入れることを意識するだけでも、自然と必要量に近づきます。
先ほど紹介した、たんぱく質量を含む食材を用いた朝昼夕の献立例をまとめましたので、参考にしてみてください。
| 日 | 食事 | 献立例 | たんぱく質量(g) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 朝 | 卵1個+納豆1パック+ごはん1膳+豆腐の味噌汁 | 約26g | 朝から植物性+動物性を両方補給 |
| 昼 | 鶏むね肉100gの照り焼き+ブロッコリー+ごはん+小鉢(ひじき) | 約32g | 鶏むねで高たんぱく&低脂質 | |
| 夜 | 銀鮭1切れ(80g)+枝豆+ほうれん草のおひたし+味噌汁 | 約24g | 魚と豆でバランスよく整える | |
| 合計 | 約82g | — | ||
| 2日目 | 朝 | ヨーグルト200g+卵1個+トースト+牛乳 | 約27g | 乳製品と卵で良質なたんぱく質を朝に |
| 昼 | 豚バラ肉100gの生姜焼き+キャベツ+ごはん+豆腐半丁 | 約34g | 肉+豆腐で満足感と栄養バランス◎ | |
| 夜 | 鯖缶1/2缶+納豆+ほうれん草+ごはん少なめ | 約22g | 消化の良い夜ごはんに調整 | |
| 合計 | 約83g | — | ||
| 3日目 | 朝 | 卵焼き(卵2個)+納豆+ごはん+味噌汁(わかめ) | 約30g | 朝からしっかり補給タイプ |
| 昼 | 鶏むね肉と豆腐のハンバーグ+サラダ+ごはん | 約33g | 肉×大豆で吸収効率UP | |
| 夜 | 銀鮭+ブロッコリー+枝豆+ごはん | 約22g | 夜は軽めに調整しながら必要量確保 | |
| 合計 | 約85g | — |
補足ポイント
- たんぱく質を1食25〜35g前後で設定し、3日平均 約83g/日になる構成。
- 動物性(肉・魚・卵・乳)と植物性(大豆製品・野菜)をバランスよく組み合わせ。
- 鶏むね・鮭・豆腐・納豆・卵などを軸にすれば、比較的コストも手間もかからず続けやすい。
まとめ
今回はたんぱく質の摂取量について学んできました。
改めてまとめです。
・たんぱく質の摂取目安は1食あたり25〜35g程度
・鶏むね肉や魚、豆製品を組み合わせて自然に摂取
・不足・過剰を防ぐには「主菜1品+豆製品」を意識
難しく考えず、日々の食事でバランスよく取り入れることが何より大切です。
健康的な体づくりのために、今日の食卓を少しだけ意識してみましょう。
今回の内容がたんぱく質を摂るために何をどのくらい食べれば良いか、皆さんの参考になれば幸いです。
たんぱく質についてより詳しく知りたい方は▼こちらの記事▼もあわせて読んでみて下さい。
▶️ 第1回|たんぱく質の働きとは? 基礎からわかる3つの役割
▶️ 第2回|1日のたんぱく質摂取量の目安は? 食材別たんぱく質量とバランスのとり方
▶️ 第3回|たんぱく質が不足・摂りすぎるとどうなる? バランスを崩すリスクと対策
あわせて読むことで、「たんぱく質の基礎から応用まで」が一通り理解できます。
それでは、今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
参考資料
- たんぱく質 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
- 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 たんぱく質
- 日本食品標準成分表2020年版(八訂)
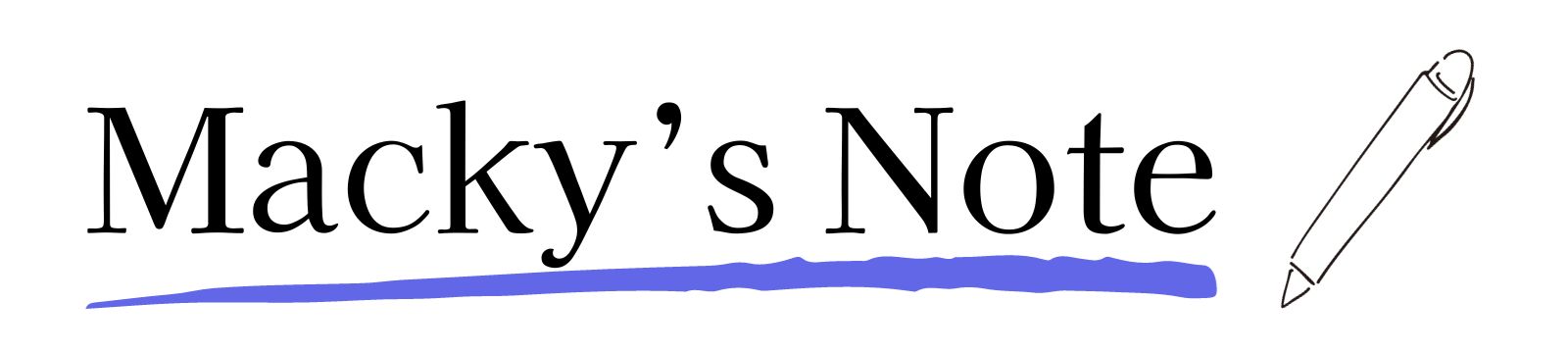



のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)