しっかり寝たのに、朝から体が重い…
布団に入ってもなかなか寝つけない
そんな“眠りの不調”を感じることはありませんか?
実は、睡眠の悩みは年齢や性別を問わずとても多く、
厚生労働省の調査でも、日本人の約4人に1人が「睡眠に何らかの問題を感じている」といわれています。
忙しい現代では、スマホやストレスなど生活習慣の影響もありますが、
意外と見落とされがちなのが「栄養」と「食べ方」の関係です。
私たちの体は、食べたものからつくられています。
眠りを導くホルモン「メラトニン」も、その材料は食事から得られる栄養素。
つまり、“何をどう食べるか”が睡眠の質を左右するのです。
寝具やアロマを工夫してもいまいち効果が感じられないとき、
もしかすると体の内側、つまり“栄養バランス”が整っていないのかもしれません。
この記事では、
・眠りを妨げる意外な原因
・ぐっすり眠るための栄養素と食材
・1日の中での取り入れ方
を、薬剤師の視点からやさしく解説します。
“寝ても疲れがとれない”日々を抜け出し、
朝スッキリ目覚めるためのヒントを、今日から一緒に見直していきましょう。
眠ってもスッキリしないのはなぜ?睡眠の質を下げる主な原因

「7時間は寝ているのに、朝がつらい」
「休日にたっぷり寝ても疲れが抜けない」
そんなとき、単なる“寝不足”ではなく、眠りの質そのものが下がっている可能性があります。
私たちの睡眠には「深い眠り(ノンレム睡眠)」と「浅い眠り(レム睡眠)」が交互に現れるサイクルがあります。
このリズムが乱れると、たとえ睡眠時間が足りていても、体や脳がしっかり休めずに朝を迎えてしまうのです。
この睡眠リズムを乱す主な原因は次の4つ。
- ストレスなどによる自律神経の乱れ
- 光やデジタル機器の刺激
- 栄養バランスの乱れ
- 生活リズムの乱れ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① ストレスなどによる自律神経の乱れ
仕事や人間関係のストレス、気温差などの小さな負担が積み重なると、
体は常に「戦う・緊張する」モード(交感神経優位)のままになります。
この状態では脳も体もリラックスできず、眠りに入りにくくなるのです。
特に就寝前まで考えごとをしたり、SNSを見続けたりすると、
“休むスイッチ”が入らずに浅い眠りが続いてしまいます。
寝る1~2時間前に約40℃のお風呂につかるとリラックスモード(副交感神経優位)となり、寝るときに自然な入眠を促します。
 まっきー
まっきー自律神経は交感神経(アクセル)と副交感神経(ブレーキ)の2つで構成されています。日中は交感神経優位、夜は副交感神経優位にすることが睡眠の質を高めるコツです
② 光やデジタル機器の刺激
スマホやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、
目を通じて脳に「今は昼だ」と誤認させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑えます。
結果として、寝つきが悪くなったり、浅い眠りが増えたりします。
また、寝る直前まで動画やSNSを見ると、情報刺激で脳が興奮状態に。
就寝の30分~1時間前にはデバイスを手放す「デジタルデトックス習慣」を。
寝室の照明も暖色系や暗めにすることで、自然と副交感神経が優位になります。



メラトニンは、強い光を浴びると分泌が低下して脳が覚醒します。分泌量が増えてくると徐々に眠気が出てきます
③ 栄養バランスの乱れ
忙しい日が続くと、つい食事が偏りがちに。
糖質中心の食事や、カフェイン・アルコールのとりすぎは、
神経の興奮を高めて眠りを浅くします。
また、睡眠に関わるトリプトファン・ビタミンB6・マグネシウムなどが不足すると、
“眠りのスイッチ”がうまく入らなくなります。
寝る前のお酒やカフェイン飲料は避け、ノンカフェインのハーブティーや白湯などを飲むと体がゆるみ、眠りに入りやすくなります。



アルコールは寝つきを良くする効果はありますが、その後早い段階で覚醒作用が出てくるため、睡眠全体としては質を下げてしまいます
④ 生活リズムの乱れ
休日の寝だめや夜更かしも、体内時計を乱す原因です。
睡眠と覚醒のリズムをつくる「体内時計」は、朝の光と朝食でリセットされます。
起きる時間・食べる時間をそろえるだけで、夜の眠気が自然に訪れます。
「毎朝同じ時間に起きる」「起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる」「朝食をとる」などの習慣を積み重ねると、眠りのリズムは少しずつ整っていきます。



朝日を浴びるのは夏場は5分程度、冬は30分程度が効果的とされています
眠りの質を整えるには
「生活リズム × 栄養バランス」の両方が大切。
寝る直前までスマホを見続けたり、夜食やカフェインをとったりすると、
せっかく眠っても浅い眠りになり、翌朝に疲れを持ち越すことになります。
逆に、朝にしっかり朝日を浴びて、バランスの良い食事をとることで、
体内時計が整い、夜の自然な眠気を引き出すことができます。



ぐっすり眠るための準備は「夜」ではなく「朝」から始めましょう
3|睡眠を支える主な栄養素


ぐっすり眠るためには、体と心のリズムを整える栄養素が欠かせません。
ここでは、睡眠に関わる代表的な栄養素と、その働きを整理してみましょう。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる | 納豆、豆腐、牛乳、バナナ |
| ビタミンB6 | トリプトファンからセロトニン・メラトニンを作る際に必要 | 鮭、鶏むね肉、にんにく |
| 鉄 | 神経伝達物質の合成を助け、日中の眠気や集中力低下を防ぐ | レバー、あさり、小松菜 |
| マグネシウム | 神経の興奮を抑え、リラックスを促す | ほうれん草、アーモンド、玄米 |
| カルシウム | 牛乳、しらす、小松菜 | |
| グリシン | 深部体温を下げて眠りの質を高める | 鶏むね肉、えび、ホタテ |
トリプトファン
まず重要なのが「トリプトファン」。
これは体内で「セロトニン」を経て「メラトニン(睡眠ホルモン)」を作る材料です。
日中にトリプトファンをとり、夜にメラトニンへと変化していくことで、自然な眠気が訪れます。
納豆や豆腐などの大豆製品、牛乳やバナナなどの手軽な食品で補えます。
ビタミンB6
次に「ビタミンB6」。
これはトリプトファンをセロトニンへと変えるために欠かせません。
不足すると、せっかくトリプトファンをとっても眠りにつながりにくくなります。
魚や鶏肉、にんにくなどを意識的に取り入れるのがおすすめです。
鉄
「鉄」は酸素を運ぶだけでなく、神経伝達物質の合成にも関わります。
鉄が足りないと、日中のだるさや集中力低下が起こり、夜の睡眠リズムも乱れやすくなります。
睡眠に関わるホルモン、「メラトニン」や「ドーパミン」の合成にも必須です。
マグネシウム・カルシウム
「マグネシウム」や「カルシウム」は、神経の興奮を抑えるミネラル。
忙しい日中に高ぶった神経を落ち着かせ、体をリラックスモードへと導きます。
特にマグネシウムはストレスによって消耗しやすいため、意識的に摂りたい栄養素です。
グリシン
最後に注目したいのが「グリシン」。
これはアミノ酸の一種で、深部体温を下げる働きがあります。
眠りにつくときは体の内側の温度が下がることで自然な眠気が訪れるため、グリシンの摂取は睡眠の質向上に役立ちます。
鶏むね肉や魚介類、ゼラチンなどに多く含まれています。
睡眠を整える栄養素は「夜だけ」ではなく、朝や昼にとることが大切。
とくにトリプトファンやビタミンB6は、日中の太陽光とともに働くことでメラトニンのリズムを整えます。
これらの栄養素は単体よりも、組み合わせて摂ることがポイントです。
たとえば「鮭+豆腐」「バナナ+ヨーグルト」など、主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせると、
セロトニンからメラトニンへの流れがスムーズになります。
睡眠の質を高めたい時におすすめの食材・メニュー


眠りを深くするには、栄養素を「どの時間帯に」「どんな組み合わせで」とるかが大切です。
ここでは、睡眠の質をサポートする食材と、実践しやすいメニュー例を紹介します。
■ 大豆製品:トリプトファンの供給源
豆腐や納豆、味噌などの大豆製品は、睡眠ホルモンの材料となるトリプトファンが豊富。
さらにカルシウムやマグネシウムも含まれ、神経を落ち着かせる作用があります。
消化が良く脂質が控えめなので、夜の食事にもぴったりです。
おすすめメニュー
- 豆腐とわかめの味噌汁
- 納豆ごはん
- 湯豆腐+小松菜のおひたし
■ 魚介類:ビタミンB6とグリシンでリズムを整える
鮭やまぐろ、さばなどの魚にはビタミンB6が多く、トリプトファンからメラトニンを作る過程を助けます。
また、えびやホタテなどに含まれるグリシンは、深部体温を下げて眠りに入りやすくする成分。
おすすめメニュー
- 鮭のホイル焼き+野菜スープ
- さばの味噌煮+豆腐の味噌汁
- えびとブロッコリーの卵炒め
■ 緑黄色野菜:自律神経を整えるミネラル補給
ほうれん草やブロッコリー、小松菜などにはマグネシウムとカルシウムが豊富。
これらは神経の興奮を抑え、リラックスを促します。
不足すると筋肉がこわばり、寝つきの悪さや夜間のこむら返りの原因になることも。
おすすめメニュー
- ほうれん草と卵のソテー
- ブロッコリーの胡麻和え
- 小松菜と厚揚げの煮びたし
■ 乳製品:メラトニン生成をサポート
牛乳やヨーグルトにはトリプトファン+カルシウムが含まれ、
寝る前の“やさしい眠りスイッチ”として効果的です。
温かいミルクは体をゆるめ、自然な眠気を誘います。
おすすめメニュー
- ホットミルク(はちみつ少量)
- バナナヨーグルト
- チーズ入り野菜リゾット
■ 発芽玄米・雑穀:GABAでリラックス
白米よりも栄養が豊富で、「GABA(ギャバ)」というリラックス成分を含むのが発芽玄米や雑穀。
血糖の乱高下を抑え、安定したエネルギー供給で夜のホルモンリズムをサポートします。
おすすめメニュー
- 発芽玄米の鮭おにぎり
- 雑穀ごはんの豆腐丼
- 玄米リゾット(野菜+チーズ入り)



睡眠の質を高めるためには、夜だけでなく朝や昼の食材選びも重要です
1日の中での取り入れ方
.jpg)
.jpg)
良い眠りは「夜だけのケア」ではなく、1日を通した食のリズムから生まれます。
朝・昼・夜、それぞれに取りたい食材を組み合わせることで、自然な眠りのリズムを整えましょう。
朝日を浴びながら、たんぱく質と炭水化物を組み合わせるのがポイント。
- パターン①:納豆ご飯+味噌汁+みかん
- パターン②:ヨーグルト+バナナ+全粒粉トースト
→ トリプトファンをとりつつ、太陽光でセロトニンがつくられ、夜のメラトニン生成につながります。
午後の眠気を防ぎつつ、ビタミンB群や鉄を意識。
- パターン①:鮭の塩焼き+玄米+野菜の味噌汁
- パターン②:鶏むね肉とブロッコリーのサラダ+全粒パン
→ 代謝をサポートし、夜に向けての自律神経の切り替えをスムーズにします。
消化の良い食材で、マグネシウムやグリシンを意識。
- パターン①:豆腐とわかめの味噌汁+鶏むね肉の照り焼き+小松菜のおひたし
- パターン②:白身魚のホイル焼き+玄米+具だくさん野菜スープ
→ リラックスを促すミネラルとアミノ酸が、深い眠りを後押しします。
「朝にたんぱく質」「昼に代謝サポート」「夜にリラックス」を意識するだけで、
体が自然と“眠りのリズム”を取り戻していきます。
まとめ|眠りの質は「日々の食事」で変えられる
眠りの不調は、特別な病気でなくても多くの人が抱える悩みです。
ですが、その多くは「生活リズム」と「栄養バランス」を見直すことで少しずつ改善していきます。
睡眠を支えるホルモンや神経伝達物質は、すべて食べたものから作られています。
トリプトファンやビタミンB群、マグネシウムなど、日々の食事に少し意識を向けるだけで、
「寝つきが良くなった」「朝スッキリ起きられる」といった変化を感じやすくなるでしょう。
また、睡眠の質が上がると、疲労回復・免疫力アップ・集中力の持続など、
翌日のコンディションにも良い影響が広がります。
無理をして完璧を目指す必要はありません。
まずは「朝にたんぱく質をとる」「夜は消化の良い食事にする」など、
できることから一つずつ取り入れてみてください。
しっかり眠れる体をつくるため、薬やサプリに頼る前に、毎日の食卓を見直してみませんか?
今日の夕食から、“眠りを育てる食事”を始めてみましょう。
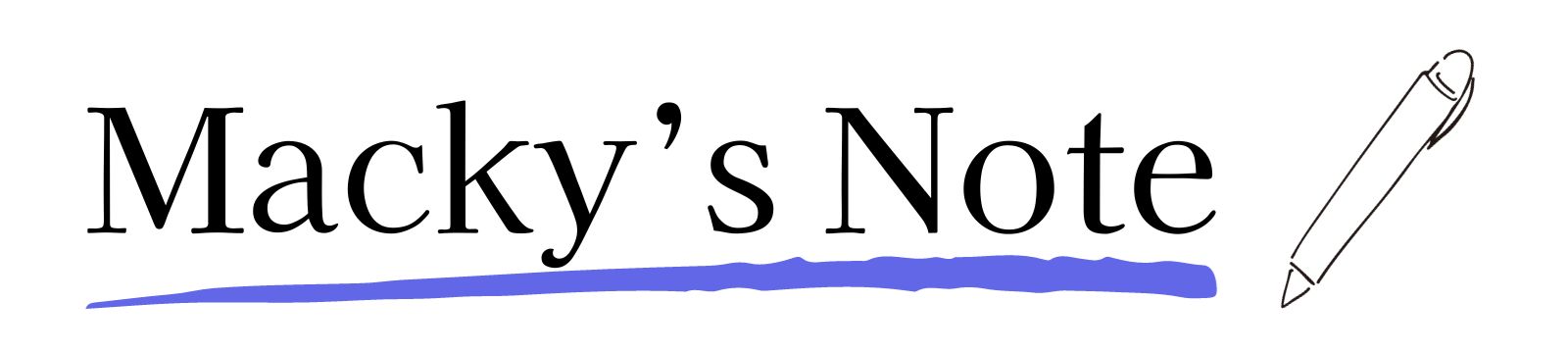
のコピー.jpg)

-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)
改-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)