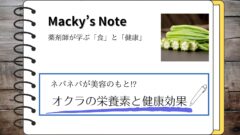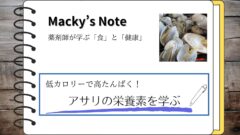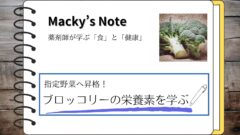秋に旬を迎えるれんこんは、シャキシャキした食感とほのかな甘みが魅力の食材です。
れんこんは腸内環境を整える食物繊維や、免疫サポートに役立つビタミンCが豊富。寒暖差が大きくなる秋は体調を崩しやすいため、季節の変わり目の健康維持にもおすすめです。
今回の記事では、れんこんに含まれる栄養素と、それらがもたらす健康効果、さらに“栄養を活かす食べ方”までを、薬剤師目線でわかりやすく解説します。
れんこんの主な栄養素

秋冬の味覚・れんこんは「栄養のバランス根菜」
れんこんは炭水化物を中心に、ビタミンC、食物繊維、カリウム、ポリフェノール類などをバランスよく含む根菜です。エネルギー補給と同時に、免疫力や腸の健康をサポートする多機能食材といえます。
ビタミンC ― 免疫ケア・疲労回復も役立つ美肌ビタミン
れんこん100gあたりには約48mgのビタミンCが含まれています。これは厚生労働省が発表している推奨量の1日100gの約半分に相当します。ちなみにれんこん100gとは小さ目の節1つ分くらいです。
ビタミンCは、免疫力を高め、肌や血管、粘膜を健康に保つために欠かせない栄養素です。コラーゲンの合成を助け、肌のハリや弾力を保つ美肌ビタミンとして知られています。
また、白血球の機能にも関与しており、ウイルスや細菌への抵抗力を高めて免疫力をサポート。さらに、ビタミンCは抗酸化作用をもち、体内で発生する活性酸素を除去することで、細胞の老化や動脈硬化などの生活習慣病リスクを減らす効果も期待されています(参考文献①)。
(*ビタミンCの働きについて詳しく知りたい方はこちらをクリック)
-240x126.jpg)
 まっきー
まっきービタミンCは水溶性なので、効率良く摂りたい時は汁物がおすすめです
食物繊維 ― 腸を整え、便秘を予防
れんこんには100gあたり約2gの食物繊維が含まれています。これは野菜の中でも比較的多い部類に入り、水溶性・不溶性の両方をバランスよく含むのが特徴です。水溶性と不溶性はそれぞれ働きが異なります。
・水溶性食物繊維:便の水分量を増加し、便を柔らかくする。腸内細菌のエサとなり短鎖脂肪酸を生成。
・不溶性食物繊維:大腸を刺激し、腸管運動を活性化
さらに水溶性食物繊維は、食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、コレステロールの吸収を抑える働きもあります(参考文献②)。
れんこんのシャキシャキとした食感は不溶性繊維によるもので、加熱しても適度な歯ごたえを残すことで満腹感が得られやすく、食べすぎ防止にもつながります。



腸活や生活習慣病予防を意識した食生活に、れんこんは取り入れやすい食材です
カリウム ― 塩分の排出をサポートし、むくみを防ぐ
れんこんには100gあたり約440mgのカリウムが含まれています。
カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、血圧の上昇を防ぐ働きをもつミネラルです。体内の水分バランスを調整する作用があり、むくみの予防にも効果的です。外食や加工食品を多く摂る人は塩分過多になりやすいため、カリウムをしっかり摂ることでバランスを保つことができます(参考文献③)。
さらに、筋肉の収縮や神経伝達にも関わっており、疲労回復や筋肉のけいれん防止にも役立ちます(参考文献④)。
れんこんは加熱調理しても風味が損なわれにくく、煮物や炒め物などさまざまな料理で無理なくカリウムを摂取できる食材です。水に溶けやすい性質があるため、煮汁ごと食べられるスープや汁物で取り入れると、効率よく摂取できます。
ポリフェノール類(タンニン) ― 抗酸化・抗炎症に貢献
れんこんに含まれる「タンニン」は、ポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用を持つ成分です。細胞の酸化ストレスを抑え、動脈硬化や糖尿病、老化など生活習慣病の予防に寄与するとされています。
MDPI誌の報告では、れんこんの抽出物にはカテキン類やエラジタンニンなど多様なフェノール化合物が含まれ、これらが活性酸素を除去する抗酸化活性に関与していることが示されています(参考文献⑤)。
また、タンニンには抗炎症作用もあり、喉や胃腸の粘膜を保護し、炎症性疾患のリスクを低減する可能性が指摘されています。さらに、タンニンは細菌の増殖を抑える性質も持ち、ピロリ菌やカンピロバクターの増殖を抑えた試験結果もあります(参考文献⑥・⑦)



タンニンの研究はヒトを対象としたものがまだ少なく、今後の発展が期待されています
このように、れんこんは見た目以上に多彩な栄養を備えた根菜です。
次の章では、これらの栄養がもたらす具体的な健康効果を見ていきましょう。
れんこんの健康効果


免疫力アップと風邪予防
れんこんにはビタミンCが豊富に含まれており、体の免疫機能を支える重要な栄養素です。
ビタミンCは白血球の働きを高め、ウイルスや細菌への抵抗力を強化します。また、強い抗酸化作用を持っているため、免疫細胞を保護することもできます。最近の研究では、1日あたり1,000mg以上のビタミンC摂取で風邪症状の重症度が約15%低減したという報告もあります。(参考文献⑧)
さらに別の研究では、植物由来のタンニンが γδ(ガンマデルタ)T 細胞を活性化。特に粘膜の γδ T 細胞応答に働き、上皮の修復や粘膜保護などにも関連している可能性も示されています(参考文献⑨)。
寒い季節にれんこんの煮物や汁物を食べることで、体を温めながら風邪の予防や疲労回復をサポートしてくれます。さらに、ビタミンCはストレスへの抵抗力を高めるホルモンの合成にも関与しているため、忙しい時期の体調維持にも役立ちます。



風邪をひきやすい秋冬に旬を迎えるので、積極的に食べたい食材のひとつですね
便秘・腸内環境の改善
れんこんには水溶性と不溶性の両方の食物繊維がバランスよく含まれています。不溶性食物繊維は腸を刺激して排便を促し、水溶性食物繊維は腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えます。
特に、れんこんのシャキッとした食感は不溶性食物繊維によるものです。日常的にれんこんを取り入れることで自然に腸の動きを促し、便秘の改善や腸内フローラのバランス維持に貢献します。
さらに近年の研究では、れんこんに含まれる水溶性食物繊維とポリフェノールの複合体、多糖類に注目が集まっています。れんこんから抽出した多糖類は腸内細菌叢を整えるだけでなく、血中の脂質量を減らすことが分かってきました(参考文献⑩)
まだ動物実験の研究が多く、ヒトでの効果は今後の検証が必要ですが、れんこんの食物繊維と多糖類が連携して、腸内環境の改善だけでなく、肥満や脂質異常の予防にも寄与する可能性を示す興味深い結果です。
むくみ・高血圧対策
れんこんはカリウムを豊富に含む野菜のひとつです。カリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあり、むくみや高血圧の予防に効果的です(参考文献③)。
外食や加工食品をよく摂る現代人は塩分過多になりがち。高血圧対策として減塩に取り組むのはもちろん必要ですが、塩分バランスを調整してくれるカリウムの摂取も併せて意識したいところです。



カリウムは水に溶けやすい性質を持つため、れんこんを汁物や蒸し料理などにすると、効率よく摂ることができます
抗酸化・抗炎症作用で生活習慣病予防
れんこんが切ると茶色くなるのは、「タンニン」というポリフェノールの一種によるものです。タンニンには強力な抗酸化作用があり、体内で発生する活性酸素を除去して細胞の老化を防ぎます。活性酸素の過剰発生は、動脈硬化、糖尿病、がんなど生活習慣病の一因とされています。
ある研究では、複数の品種のれんこんを比較し、ポリフェノール類が非常に多く含まれること、特にカテキンやエラジタンニンなどが強い抗酸化能を示すことが報告されています。これらの成分は、体内の炎症反応を抑え、血管や臓器の健康を守る働きがあると考えられています(参考文献⑤)。
肌の健康維持
れんこんは「内側からのスキンケア」にも役立つ食材です。
れんこんにはビタミンCとタンニンなどのポリフェノールがともに含まれているため、抗酸化作用が期待できます。タンニンが直接的な美容効果を示す研究は少ないものの、タンニンの持つ抗酸化作用により紫外線やストレスによる肌の酸化ダメージを防ぎ、シミやくすみなどの肌トラブルを防ぐ成分として注目されています。
さらにビタミンCはコラーゲンの生成をサポート。肌のハリや弾力を維持するのに役立ちます。



冬場の乾燥や冷えによる肌不調が気になる時期には、れんこんを食事に取り入れることで、美肌づくりを内側から助けてくれます
このようにれんこんは、免疫・腸・血圧・美容と多方面に働く「バランス型の健康食材」です。
次章では、栄養をしっかり活かすための調理のコツや食べ方を紹介します。
れんこんの栄養を活かす食べ方と調理のコツ


れんこんはさまざまな料理に活用できる食材です。ただし、調理法によって引き出せる栄養や風味は少しずつ異なります。
シャキシャキ感を生かすなら短時間の加熱、ホクホクに仕上げたいならじっくり火を通すのがおすすめです。また、タンニンは空気に触れると酸化して黒く変色しますが、酢水に軽くさらすことで色をきれいに保てます。
煮物、炒め物、汁物、すりおろしなど、料理の目的に合わせて調理法を選ぶと、れんこんの健康効果をより高められます。
れんこんの栄養を活かす調理のコツ
| 栄養素・成分 | 調理のポイント | 効果を高める食べ方 |
|---|---|---|
| ビタミンC・カリウム | 水に溶けやすい | スープや味噌汁など、煮汁ごと食べられる料理がおすすめ |
| 食物繊維 | 加熱しすぎず食感を残す | 炒め物やきんぴらでシャキッと仕上げる |
| タンニン(ポリフェノール) | 酢水にさらして色を保つ | 酢れんこんやサラダで抗酸化作用を活かす |
このように調理の工夫ひとつで、れんこんの栄養価をより効果的に取り入れられます。
まとめーれんこんで内側から元気に秋を乗り切ろう
れんこんは、ビタミンCや食物繊維、カリウムなどをバランスよく含む栄養豊富な根菜です。免疫力アップや腸活、むくみ予防など多方面で健康をサポートします。季節の食卓に取り入れて、心も体も温まる栄養補給をしましょう。
参考文献
- Vitamin C: A Comprehensive Review of Its Role in Health, Disease Prevention, and Therapeutic Potential
- Chronic Constipation: Is a Nutritional Approach Reasonable?
- 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」ミネラル(多量ミネラル)
- Regulation of muscle potassium: exercise performance, fatigue and health implications
- Phenolic Profiles and Antioxidant Activity of Lotus Root Varieties
- Bactericidal effect of hydrolysable and condensed tannin extracts on Campylobacter jejuni in vitro
- Antibacterial activity of hydrolyzable tannins derived from medicinal plants against Helicobacter pylori
- Vitamin C reduces the severity of common colds: a meta-analysis
- Response of gammadelta T Cells to plant-derived tannins
- Complexes of Soluble Dietary Fiber and Polyphenols from Lotus Root Regulate High-Fat Diet-Induced Hyperlipidemia in Mice
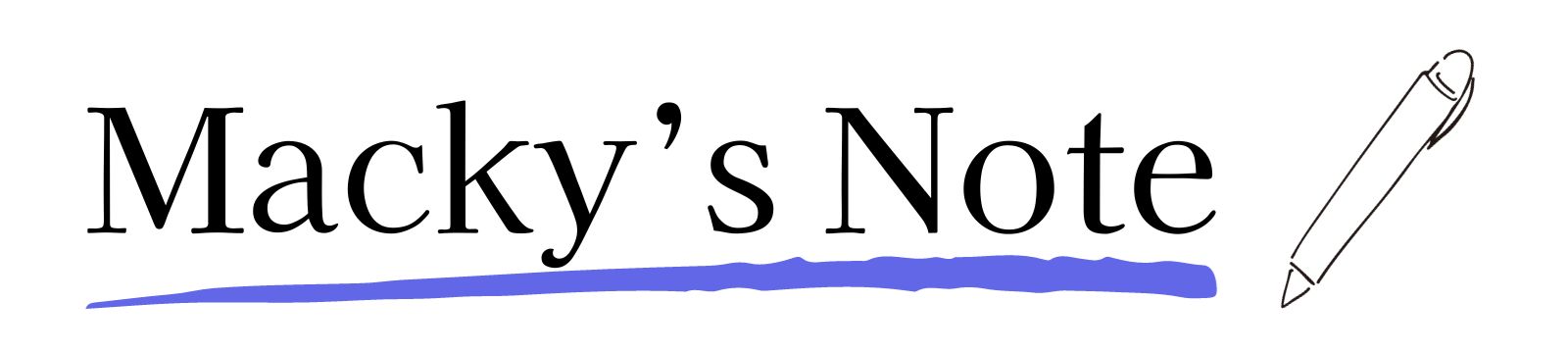
.jpg)

改-240x126.jpg)
-240x126.jpg)