こんにちは、薬師のまっきーです。
今回は夏野菜としておなじみのオクラ。独特のネバネバで好き嫌いが分かれる食材ですが、実はその粘り成分こそが美容や健康にうれしい栄養素のかたまりなのです。
本記事では、薬剤師の視点からオクラに含まれる成分の美容・健康への作用について学んでいきます。
オクラの栄養素と生理作用

水溶性食物繊維
オクラの特徴と言えば、独特のネバネバですよね。あのネバネバの正体は食物繊維。オクラ100gあたり5gも含まれているんです。
 まっきー
まっきー一般的なサイズのオクラは
1本で約10gです
オクラに含まれている食物繊維はペクチンやガラクタンなどの水溶性食物繊維で、次のような効果が期待できます。
- 腸内環境改善
水溶性食物繊維は腸内でゲル化し、便のかさを増やしつつ便通を調整します。また、善玉菌のエサとなって短鎖脂肪酸を産生させることで腸内のバリア機能を向上させます。 - 血糖値調整
消化管内で糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値上昇を穏やかにします。糖尿病予防やインスリン抵抗性改善への可能性が報告されています。 - 粘膜保護
ネバネバの成分であるガラクタンやアラバンなどの多糖類は、胃粘膜を覆い炎症を緩和する作用が示唆されています。



以前は「オクラのネバネバ成分はムチン」と言われていましたが、最近の研究でムチンが含まれていないことが判明しました
ビタミンC
- 抗酸化作用
活性酸素を中和し、細胞膜やDNAへの酸化ストレスを軽減。免疫機能の維持や紫外線によるシミなどの皮膚トラブル抑制も期待できます。 - コラーゲン合成促進
コラーゲン合成過程の補酵素として作用。肌のハリやツヤの維持に関与します。



コラーゲン合成にはビタミンCの他に鉄分も大切です
β-カロテン
β-カロテンとは体内でビタミンAに変化する栄養素で、植物性食品に含まれます。
- 抗酸化作用
活性酸素の働きを抑え、動脈硬化などの生活習慣病予防やアンチエイジングも期待できます。 - 皮膚・粘膜保護
上皮細胞の分化や成長に関与し、のどや鼻、消化管の粘膜を正常に保ちます。



のどや鼻の粘膜を保護することは感染症対策にも重要です
カリウム
- ナトリウム排泄促進
余分な塩分(ナトリウム)排泄を高め、血圧を低下させる作用があります。塩分の摂り過ぎによるむくみの軽減にも効果的です。 - 筋肉の収縮・弛緩
神経細胞や筋肉の電気信号に関与し、筋肉の収縮や弛緩を制御します。



足がつりやすい人は水分とカリウムの摂取量が不足していないか注意してみましょう
オクラの美容効果


オクラの持つ美容効果に着目してまとめてみます。
- 美肌効果
オクラに含まれるビタミンCとβ-カロテンは、抗酸化作用によりシミ・シワを予防します。さらにビタミンCによるコラーゲン合成促進でハリ・弾力のある肌へ。
また、オクラに含まれる水溶性食物繊維は腸内細菌叢を整えます。便秘や腸内フローラの乱れはニキビや肌荒れの原因となるため、食物繊維を摂取することで肌状態の改善につながります。 - むくみ予防
オクラに含まれるカリウムは体内の余分な塩分排泄を促し、水分バランスを調整します。水分の滞りも改善するため、フェイスラインをすっきりさせ、脚のむくみ対策にも有効です。 - 美髪効果
オクラに含まれるβ-カロテンは新陳代謝を促し、髪をつくり出す毛根細胞を活性化します。また、ビタミンCやビタミンB群も頭皮への血流を改善し、髪に必要な栄養素を届けるサポート。コシやツヤのある髪をつくります。
オススメの食べ方


オクラに含まれる栄養素は水溶性の栄養素が多いため、長時間水にさらすと栄養素が逃げてしまいます。そこで、オクラの栄養素を効率良く摂取するためのオススメの食べ方を紹介します。
調理方法
- 生食
ビタミンCは熱に弱いため、ビタミンCを効率良く摂りたいなら生のままがオススメです。うぶ毛の処理は必要ですが、細かく刻んでサラダや和え物にすることで、栄養を損なわずに摂取できます。 - 加熱
長時間ゆでると栄養素が逃げてしまうので、加熱する時は蒸したりさっとゆでたりするのが良いでしょう。電子レンジ加熱も栄養保持に有効です。



スープはゆで汁に溶けだした栄養素ごと食べられるので◎
食べ合わせ
- 発酵食品との組み合わせる
納豆やキムチなどの発酵食品と併せることで腸内環境改善効果を相乗的に高めます。 - 油脂と合わせる
β-カロテンは脂溶性のため、オリーブオイルやごま油と一緒に摂ると吸収効率が上がります。
おわりに
オクラは、水溶性食物繊維・ビタミンC・β-カロテン・カリウムといった栄養素を豊富に含み、腸内環境改善・美肌形成・むくみ予防・抗酸化作用など、美容と健康の双方に有益な野菜です。日常的に取り入れることで、体の内側から健康と美容をサポートしてくれるでしょう。
スーパーなどでは冷凍オクラも売られているので、夏以外にも日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
それでは今回はここまで。最後までお読みいただきありがとうございました!
参考資料
・02_各論_1-4_炭水化物_cs6_0116.indd (mhlw.go.jp)
・チュニジアオクラのさや(Abelmoschus esculentus L. Moench)の化学組成、栄養価、および生物学的評価-PMC
・フロンティア |前糖尿病および糖尿病におけるオクラベースの治療の心臓代謝上の利点:ランダム化比較試験の系統的レビューとメタ分析
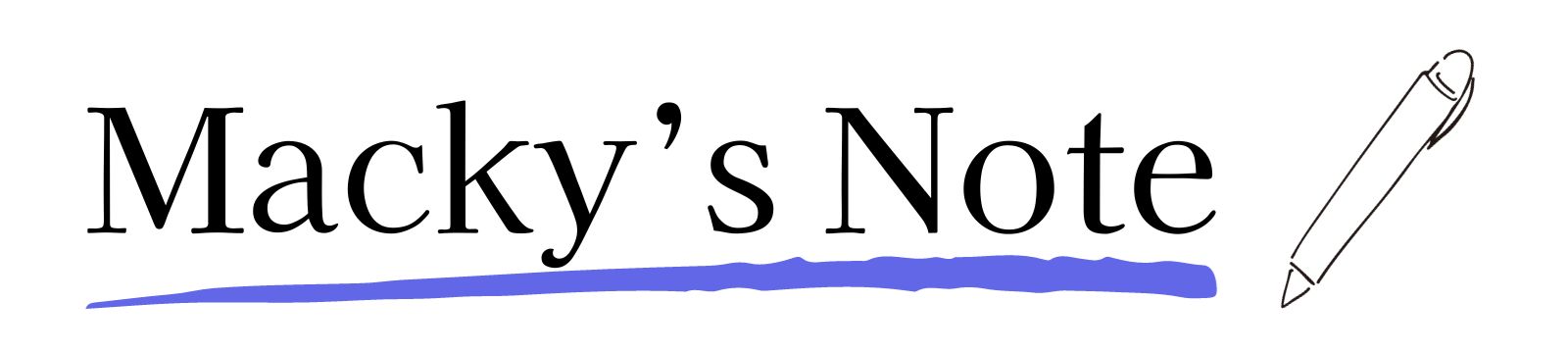
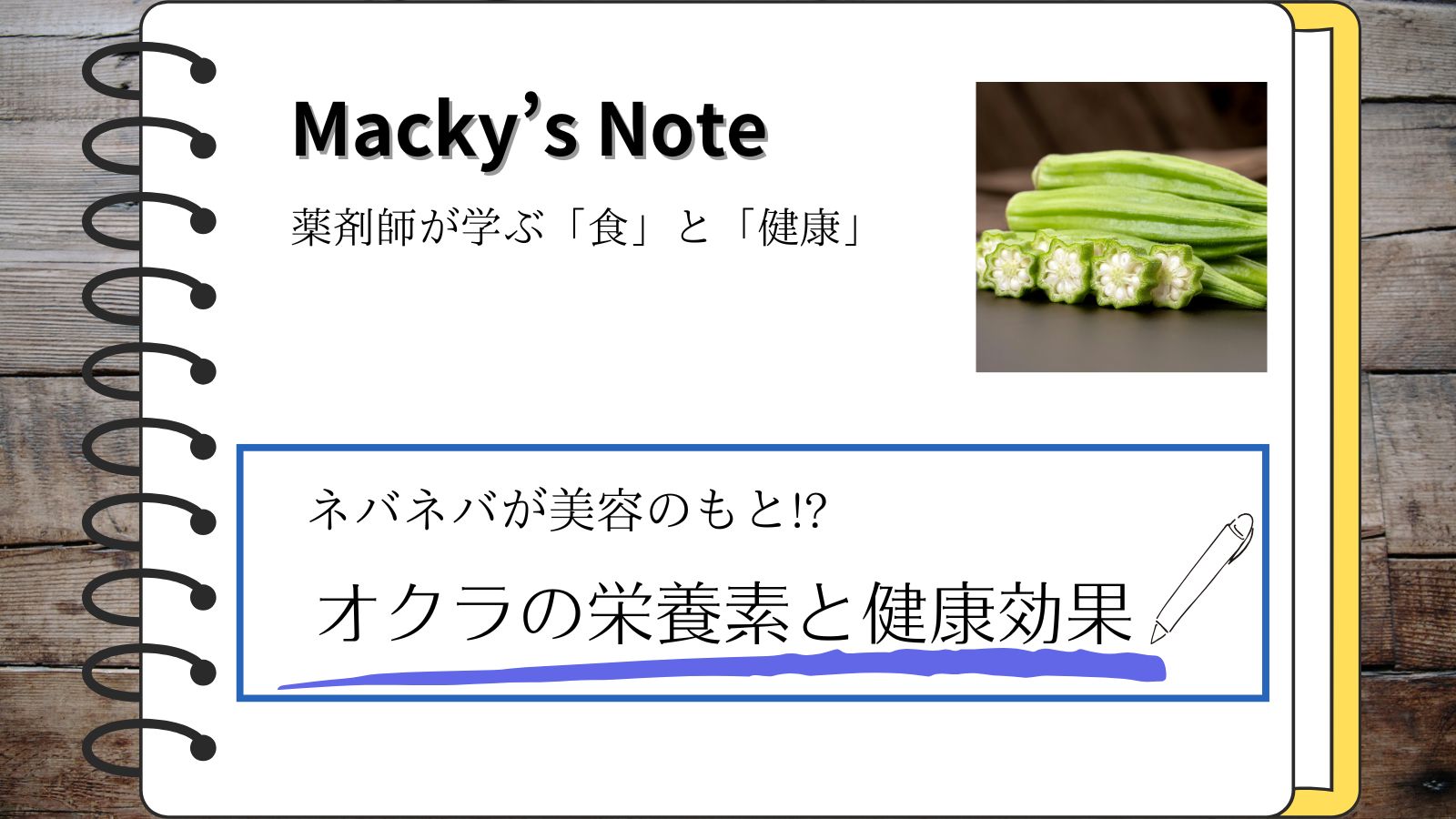
-240x126.jpg)
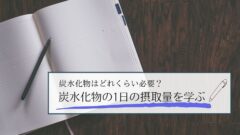
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)