脂質にも“良し悪し”があるって知っていますか?健康的に脂質を摂るためには、脂肪酸の種類を理解することが大切です。誤解されることも多い脂質について正しく知るために、3ステップで解説していきます。
3回目の今回は、体に良い脂質・控えたい脂質を見分けるポイントを学んでいきましょう。
良い脂質や悪い脂質ってどんな脂質?
不飽和脂肪酸やトランス脂肪酸ってどんな特徴があるの?
良い脂質を摂るコツは?
こんな疑問に対して、薬剤師がわかりやすく解説していきます。
▼この記事でわかること▼
・脂質の良し悪しは脂肪酸の種類で決まる
・良質な脂質:体にとって良い働きをする脂肪酸
例)不飽和脂肪酸、中鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸
・悪質な脂質:体にとって悪い働きをする脂肪酸
例)長鎖脂肪酸、トランス脂肪酸
・良質な脂質を摂るコツは、植物由来の油を使用し、魚・ナッツ・アボカドなどを取り入れる
より詳しく知りたい方はぜひ最後まで読んでみてください。
「脂質を正しく知る3ステップ」
──健康維持に欠かせない“脂の真実”を学ぼう
▷第1回|脂質の働きと種類をわかりやすく解説
▷第2回|脂質はどのくらい摂ればいい?
▷第3回|良質な脂質・悪質な脂質の違いとは?
良質な脂質・悪質な脂質の違い

良質な脂質と悪質な脂質は何が違うのでしょうか?
その答えは脂肪酸の違いにあります。
私たちの体や食品に含まれている脂質には中性脂肪やコレステロール、リン脂質などいくつか種類がありますが、最も多いのが中性脂肪です。
中性脂肪を構成しているのは、グリセロールという成分と3つの脂肪酸。
この脂肪酸にはいくつか種類があり、それぞれに特徴があります。
体にとって良い働きをする脂肪酸を多く含むもの→良質な脂質(健康維持に役立つ脂質)
体にとって悪い働きをする脂肪酸を多く含むもの→悪質な脂質(摂取を控えたい脂質)
食品によって、含まれている脂肪酸の種類や量が異なります。
 まっきー
まっきー食品を選ぶ時は、どんな脂肪酸が含まれているのか意識したいですね
良質な脂質(健康維持に役立つ脂質)


良質な脂質と呼ばれる、体にとって良い働きをする脂肪酸はどんなものがあるでしょうか?
簡単にまとめてみました。
①不飽和脂肪酸
心筋梗塞など循環器疾患の発症リスク低減の可能性あり
②中鎖脂肪酸
素早くエネルギー源として利用され、体脂肪になりにくい
③短鎖脂肪酸
腸内環境の改善のほか、代謝や免疫力向上に関与
悪質な脂質(摂取を控えたい脂質)


悪質な脂質と呼ばれる、体にとって悪い働きをする脂肪酸はどんなものがあるか、簡単にまとめました。
①長鎖脂肪酸
エネルギー源として利用されるが、過剰になるとLDL(悪玉)コレステロールを上昇させる
②トランス脂肪酸
人体での有用性はなく、心臓病の発症リスク上昇などの報告あり



特にトランス脂肪酸は摂取しても体にとってデメリットしかないので、なるべく避けたいですね
脂肪酸の種類と特徴


脂質の良し悪しを決める脂肪酸。
脂肪酸にはどんな種類と特徴があるのでしょうか?
脂肪酸の種類ごとに特徴をまとめたので、ご覧ください。
飽和脂肪酸
長鎖脂肪酸(ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸)
- エネルギー源として利用される
- 過剰になるとLDLコレステロール値上昇のリスクあり
- ラード、バター、肉類の脂などに多く含まれる



一般的に言われている飽和脂肪酸は、長鎖脂肪酸のことを指していることが多いようです
中鎖脂肪酸(ラウリン酸、オクタン酸、テカン酸)
- 水に溶けやすく消化吸収性に優れている
- 代謝が早くほとんどがエネルギー源として利用されるため、体脂肪になりにくい
- 過剰摂取では胃痛や下痢などを起こすリスクあり
- ココナッツオイル、パームオイル、MCTオイルなどに含まれる
短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸)
- 大腸のエネルギー源となる
- 腸上皮細胞の新陳代謝を上げる
- スムーズな排便と腸のバリア機能に関与
- 食物から直接摂取も可能だが小腸で吸収されるため、腸内細菌が生成するものを利用した方が上記効果を得やすい



腸内細菌の短鎖脂肪酸合成を促すには、乳製品や食物繊維、オリゴ糖の摂取がオススメです
不飽和脂肪酸
一価不飽和脂肪酸(パルミトレイン酸、オレイン酸)
- エネルギー源として利用される
- 酸化しにくく、過酸化脂質になりにくい
- オリーブ油、キャノーラ油、サラダ油などに含まれる



過酸化脂質は体に悪影響を及ぼすと考えられています
n-6系脂肪酸(リノール酸、γ-リノレン酸、アラキドン酸)
- 多価不飽和脂肪酸の1つ
- LDL(悪玉)コレステロールを減少させるが、過剰摂取ではHDL(善玉)コレステロール減少リスクあり
- 極端な摂取不足では皮膚炎等を生じることがある
- 摂取基準は成人男性:8〜11g 成人女性:7〜8g
- レバー、卵白、ナッツ類、アボカドなどに含まれる
n-3系脂肪酸(EPA、DHA、α-リノレン酸)
- 多価不飽和脂肪酸の1つ
- HDL(悪玉)コレステロール上昇、中性脂肪を減少させる
- 極端な摂取不足では皮膚炎等を生じることがある
- 摂取基準は成人男性:2.0〜2.2g 成人女性:1.6〜2.0g
- マグロ、サンマ、サバなどの魚類やエゴマなどに含まれる



n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸は体内で合成できないため、食品から摂取する必要があります
n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。


トランス脂肪酸
- 脂肪酸の1種
- 牛肉や羊肉、乳製品に含まれる天然のものと、油脂の加工・精製でできるものがある
- 人体での有用性は知られてない
- LDL/HDL比の上昇、心臓病の発症リスク上昇あり
- WHOでは摂取エネルギー量の1%未満とすることを推奨



人体への悪影響が示唆されているのは、油脂の加工・精製でできるトランス脂肪酸です
良質な脂質を上手に取り入れるコツ


良質な脂質を意識するポイントは、「油の種類」と「調理法」の2つです。
- 油の種類:オリーブ油やえごま油など植物由来の油を中心に、バターやラードなど動物性脂肪は控えめに。
- 食材選び:主菜に魚を週2回以上。ナッツやアボカドをおやつ代わりに。
- 調理法:揚げるより「焼く・蒸す・和える」を選ぶだけでも脂質の質が改善します。
難しく考えず、日々の食卓で“油の質”を少し意識してみるところから始めてみましょう。
まとめ
今回は良質な脂質と悪質な脂質の違いと、脂肪酸の種類ごとの特徴を学んできました。
改めてまとめです。
・脂質の良し悪しは脂肪酸の種類で決まる
・良質な脂質:体にとって良い働きをする脂肪酸
例)不飽和脂肪酸、中鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸
・悪質な脂質:体にとって悪い働きをする脂肪酸
例)長鎖脂肪酸、トランス脂肪酸
・良質な脂質を摂るコツは、植物由来の油を使用し、魚・ナッツ・アボカドなどを取り入れる
長鎖脂肪酸は体に必要な脂質量を得るために、ある程度の摂取は必要です。
ですが、近年では長鎖脂肪酸の摂取量が増加傾向にあり、心筋梗塞などの循環器疾患の発症リスクを上げる要因と指摘されています。肉類や揚げ物中心の食生活を送っている方は、魚を取り入れるなどバランスの見直しがオススメです。
脂質についてより詳しく知りたい方は▼こちらの記事▼もあわせて読んでみて下さい。
「脂質を正しく知る3ステップ」
──健康維持に欠かせない“脂の真実”を学ぼう
▷第1回|脂質の働きと種類をわかりやすく解説
▷第2回|脂質はどのくらい摂ればいい?
▷第3回|良質な脂質・悪質な脂質の違いとは?
あわせて読むことで、「脂質の基礎から応用まで」が一通り理解できます。
それでは今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
参考資料
脂肪 / 脂質 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
00_1_表紙_cs6_1220.indd (mhlw.go.jp)
不飽和脂肪酸 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
すぐにわかるトランス脂肪酸:農林水産省 (maff.go.jp)
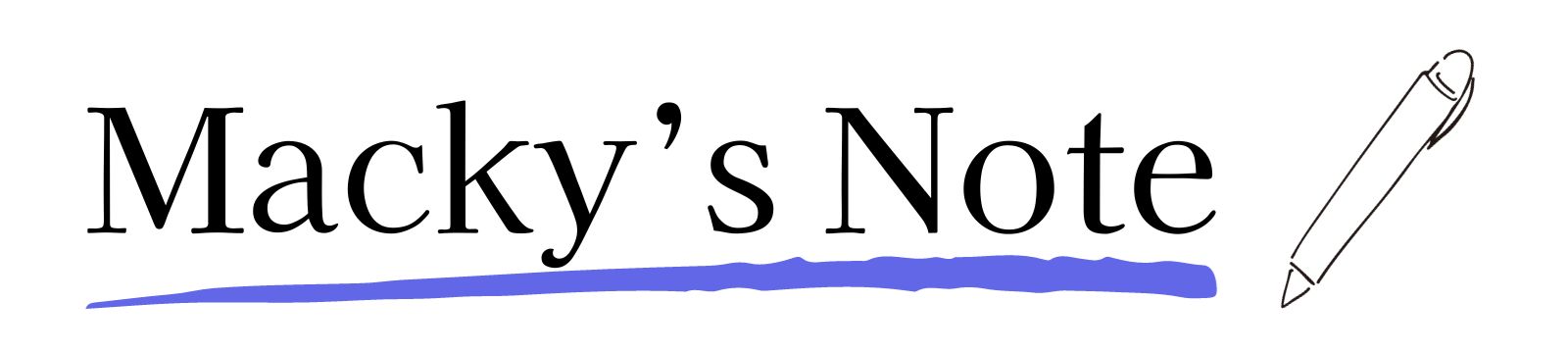


のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
のコピー-240x126.jpg)
-240x126.jpg)
-240x126.jpg)